おぎにゃん
劇場作品の『Paprika』や『PERFECT BLUE』(注8)、TVシリーズの『妄想代理人』(注9)など、橋本さんは今 敏監督の作品でたくさん色彩設計のお仕事しているにゃ。今は『DEATH NOTE』で荒木監督と組んでいるけど、監督によってやり方は違うのにゃ?
橋本
「ぜんぜん違う!」って言える。まず、要求するレベルが監督によって異なる。そして、監督がその作品作りで「何を大事にしているか」によってまた変わってくる。演出レベルの話まで含めて、監督の求めているものは何なのか、どんな空気感なのか、といった部分が深く関わってくる。
おぎにゃん
色彩関係だと、おぎにゃんは「光や色といえばりんたろう監督」(注10)ってイメージがあるにゃが、りんたろう監督だとやっぱり要求するレベルは高いにゃ?
橋本
高いよ。でも、出来上がるまでは「こんな感じで」というざっくりとした指示であまり口を出さない。「好きにやって」って感じ。それで最後に出来上がったものを見て「いい」「悪い」と判断するやり方だから、けっこうやりがいがある。
おぎにゃん
それが、監督が変わると違うんだにゃ。
橋本
おぎにゃんは、今 敏監督の絵コンテを見たことある?
おぎにゃん
あるにゃ! めちゃくちゃ綿密に描いてあるにゃ!
橋本
でしょう? あの絵コンテを見ればたいていのことがわかるようになっている。画面の構図の取りかた、演出の意図、話の流れなど監督のイメージがすべて絵コンテに集約されているからね。監督のイメージがかなり出来上がっているので、作業するほうとしては絵コンテレベルより下のものは出せないね。
おぎにゃん
でも、絵コンテはモノクロにゃ。『Paprika』はとても発色がよかったけど、それは橋本さんが考えたのにゃ?
橋本
パレードのシーンなんかはイっちゃってる人の精神世界の話だから「イっちゃってる感じにしたい」という監督の要望があって、自分はそれに沿って作った。今 敏監督の場合、今までは逆にトーンを控えめの作品が多かった。『千年女優』(注11)とか、モノクロかいな(笑)みたいな。
おぎにゃん
全体的に落ち着いた感じのイメージがあるにゃ。
橋本
そのあたりは、監督がどんなものを作りたいかが色彩にも反映されてくるんだ。今 敏監督の場合、今までマッドハウス作品でずっと一緒にやらせてもらってるけど、毎回新しいアプローチがあってとても刺激になる。だいたい、いい意味でも悪い意味でも「いつもの感じ」「その監督のカラー」というのが出てくるけど、今 敏監督の場合は細かい味付けの仕方が毎回違うからね。
おぎにゃん
常にチャレンジャーにゃんだな。
橋本
『DEATH NOTE』の場合は、荒木監督始めての長編なので、こちらもなかなかおもしろい。
おぎにゃん
全体にダークな感じっていうコンセプトがあるにゃ?
橋本
『DEATH NOTE』で色彩が鮮やかすぎても迫力がでない。「あいつ殺そう」って場面なのに、やけに画面がピカピカキラキラしてたら、雰囲気ない(笑)。
おぎにゃん
爽やかデスノートにゃ!
橋本
あとTVシリーズなので、劇場版とはまわりの環境も違うしね。
おぎにゃん
環境が違うって?
橋本
劇場版だと、まわりのスタッフたちがやはり実力者ぞろい。だけどTVシリーズは、時間も予算も劇場版に比べて少ないし、毎回お願いしたい人を呼べるわけではない。だからどうしても色彩設計が、色指定や仕上げのフォローをする比率が高くなる。
おぎにゃん
イメージとして作画監督が原画をフォローする感じだにゃ。
橋本
やっぱり、アニメーション制作は合同作業だから、誰か一人がうまいだけじゃダメ。全体的に、どれだけ作品に合ったスタッフを集められるか、というのが間違いなく作品クオリティを左右するよ。
おぎにゃん
共同作業っていう部分では、どうやら色彩設計は、色指定や仕上げのほかに美術との絡みが多そうだにゃ。
橋本
あと、撮影とかね。
おぎにゃん
それぞれ、どんな連携をとっているのか教えて欲しいにゃん。
橋本
前編で少し説明したけど、美術とはボードについて打ち合わせる。作業段階的には最初のほうになるね。はじめの美術打ち合わせで、監督や美術と色彩設計が一緒になって「どんなイメージのボードをあげるか」を話し合う。例えば「落ち込み気味の雰囲気が欲しいなら、影をちょっと落とし気味にする」とか「希望がある画面ならもっと光をたくさんもらった方がいいんじゃないか」といったことを検討する。
おぎにゃん
じゃあ色彩設計が背景も指定するにゃ?
橋本
シーンによってはキャラクターの心象風景もあるでしょう。そこで監督が「ここはキャラクターが落ち込み気味だから、ブルートーンがいい」と言ったとする。そういう場合に「前のシーンも似たようなテイストなので、ガラッと変えたほうがいいのでは?」みたいに口をはさむことはあるよ。でも、だいたい美術に関しては監督と美術がメイン。色彩設定は自分の立場から意見を言う程度だよ。
おぎにゃん
そこで決まったボードにキャラクターをどう馴染ませるかが、メインにゃんだな!
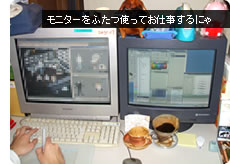 橋本 橋本
そうだね。色彩設計はキャラクターの色の総責任者だから、背景色にも関わってくるんだよ。で、撮影との連携は作業的には最後のほう。色彩設計が背景に合わせてキャラクターの色変えをした後に、撮影が背景もキャラクターも合わせた画面全体の色を落としたり、彩度をあげたりする。詳しいことは撮影の回で聞いてね。
おぎにゃん
色彩設計が細かく色を調整していて、それを撮影は背景と一緒に演出意図にそって全体のバランスを整える、って感じ?
橋本
おおまかに言えばそうだね。だから明るさの調整を撮影に任せることもできるんだけど、色彩設計で担当した方が細かいコントロールが効いていいんだよ。それに、撮影はアニメーション制作では最後のほうの部署になるから、前段階にある色彩設計が作業を受け持っているほうが効率が良いし。
おぎにゃん
なるほどにゃ〜。他には原画マンと関わったりとかもするにゃ?
橋本
例えば、DVDのジャケットイラストなどの版権ものは、描き手の原画マンに「どういうコンセプトで描いたのか」を聞いて作る。キャラクターが奥と手前にいる構図だったら、原画マンが奥のキャラクターの色を明るめにして、手前のキャラクターの色を落としめにしたい、とか考えて描いてる場合もあるから。
おぎにゃん
どうしてにゃ?
 橋本 橋本
どちらも同じ明るさだと、こんな感じになる(イラスト参照)。
おぎにゃん
手前にお師匠がいて、後ろをおぎにゃんが歩いているにゃ。
橋本
 これだと、手前にいる分アニメ仙人のほうが目だつよね。でも、原画マン的には後ろを歩いているおぎにゃんを目立たせたいかもしれない。そうしたらアニメ仙人の色を落とすんだ。すると、自然と目が後ろにいく(イラスト参照)。 これだと、手前にいる分アニメ仙人のほうが目だつよね。でも、原画マン的には後ろを歩いているおぎにゃんを目立たせたいかもしれない。そうしたらアニメ仙人の色を落とすんだ。すると、自然と目が後ろにいく(イラスト参照)。
おぎにゃん
一気に、おぎにゃんが主人公になったにゃ!
橋本
このへんの色彩は、原画マンと「この絵はどうしたいですか?」って話をして決めるよ。
おぎにゃん
そういえば、『DEATH NOTE』のDVD第6巻(レンタル用)がそんな構図のジャケットだったにゃぁ。チェックしてみるにゃ。
橋本
それとキャラクターが違えば、肌色も違う。そういう細かい部分は普段あまり意識されないけれど、アニメーションのクオリティに関わっているからね。
おぎにゃん
にゃ! ところで、橋本さんは『Paprika』が終わってから『DEATH NOTE』に?
橋本
終わりそう……くらいのときから。『Paprika』の制作期間とかぶっていたので、そっちもやりつつ『DEATH NOTE』も、って感じだったんだ。
おぎにゃん
色彩設計の人たちは、皆さんそんな感じなのかにゃ?
橋本
だいたいの色彩設計は、前作品とオーバーラップするかたちで次の作品を入れるってケースが多い。ある作品が終了してそれから次を探すと、どうしても間が空いてしまうからね。
おぎにゃん
TVシリーズの掛け持ちはするにゃ?
橋本
フリーの人は最低2本は抱えていると思う。1本だと、生活できないレベルではないにしろ儲からないから。だいたい2〜3本がオーソドックスかなぁ。
おぎにゃん
色彩設計の人にも色んなタイプがあると思うにゃが、人によって方向性の違いはあるにゃ?
橋本
人によって得意分野は違う。シリアスなのが得意だったり、ギャグものが得意だったり。そういうのはあると思うよ。自分はリアル系が好きなので、自然とそちらの仕事がやりたくなる。逆に依頼がくれば引き受けるけれど、魔法少女ものみたいな作品はあまり得意じゃなくて、そういう作品はそこに特化した人が受け持ったほうがいいと思う。
おぎにゃん
畑が違うんだにゃ。
橋本
「この人に頼むとこういうレベルのものがあがってくる」「こういう傾向の作品になる」という違いはあるし、色彩設計のオリジナリティーとしても大事な要素。それと、制作の結果だけじゃなく、作っていく過程でコミュニケーションを上手くやっていける人かどうかも重要だと思う。制作途中ではしんどいことも多々あるし、すごい人数が関わっているわけだから、人間性の部分も問われてくる。そういった人間性と作品の結果が評価対象じゃないかな。
おぎにゃん
なるほどにゃ! アニメーションはチーム作業だものにゃ! 橋本さん今日はありがとうございましたにゃん!
|